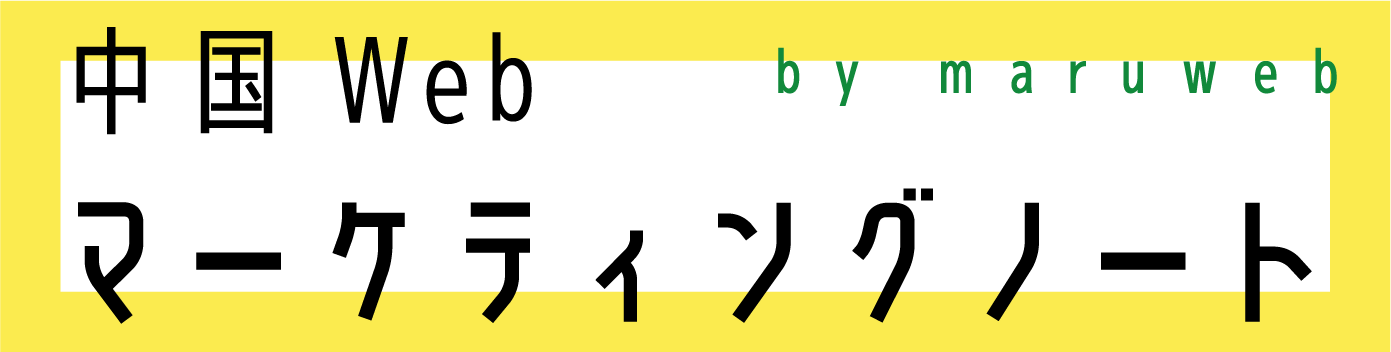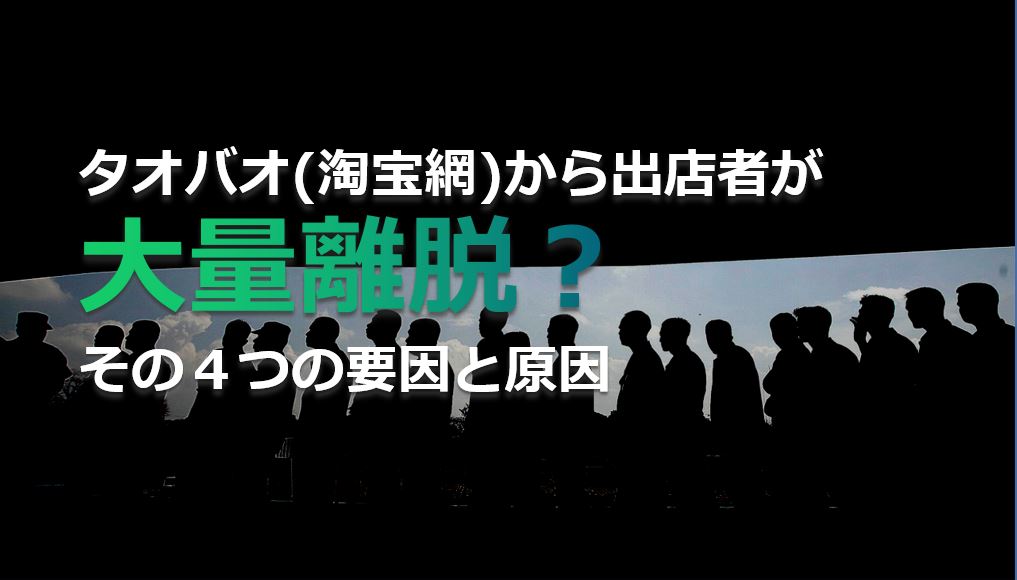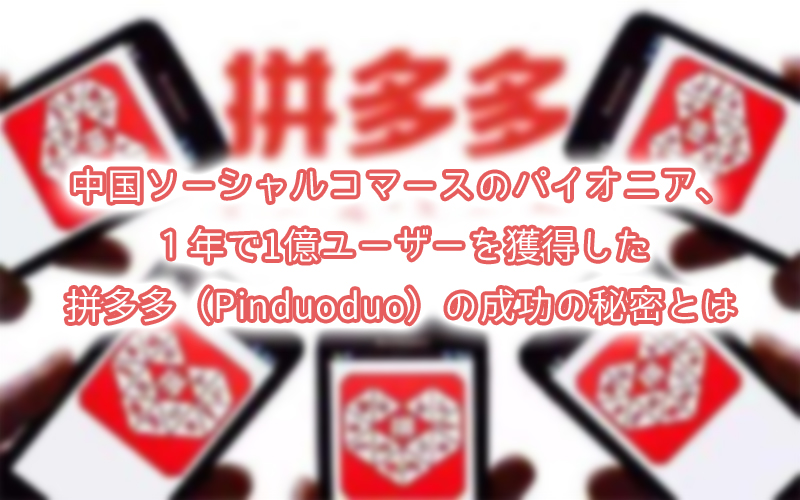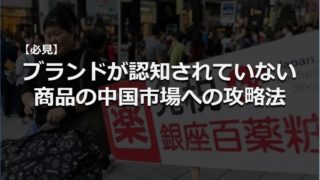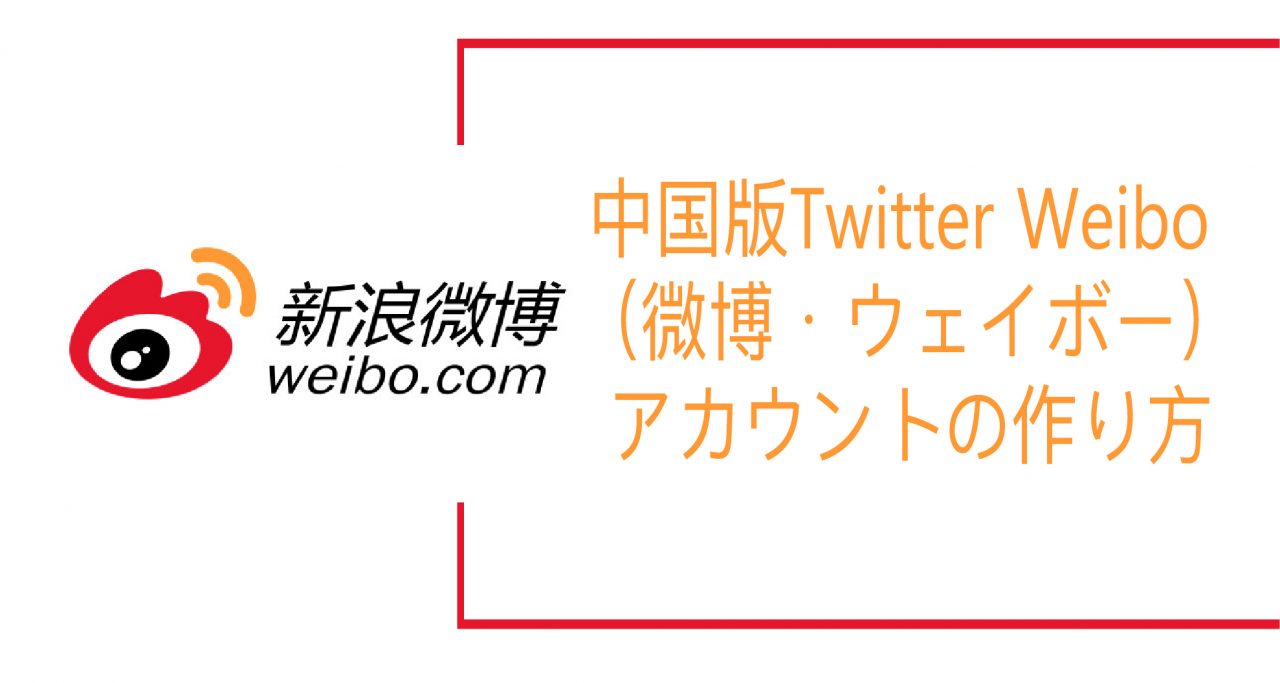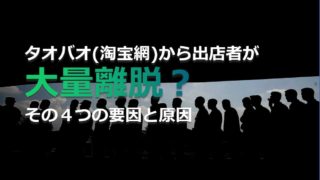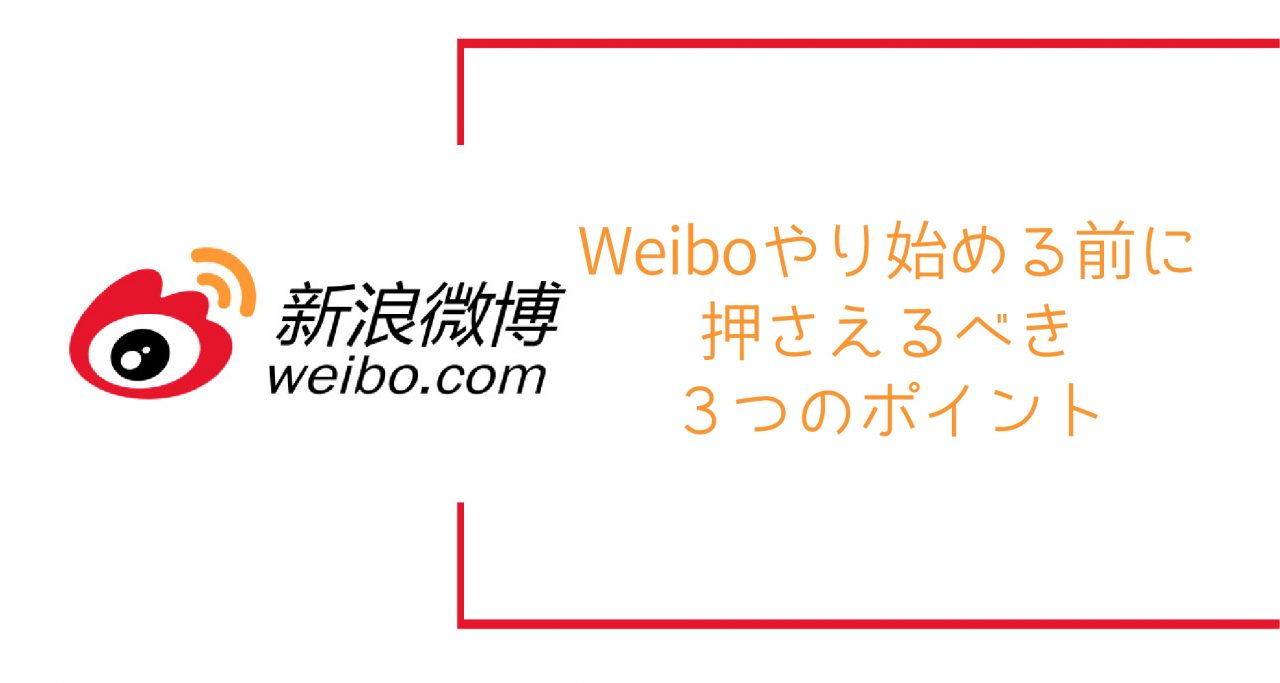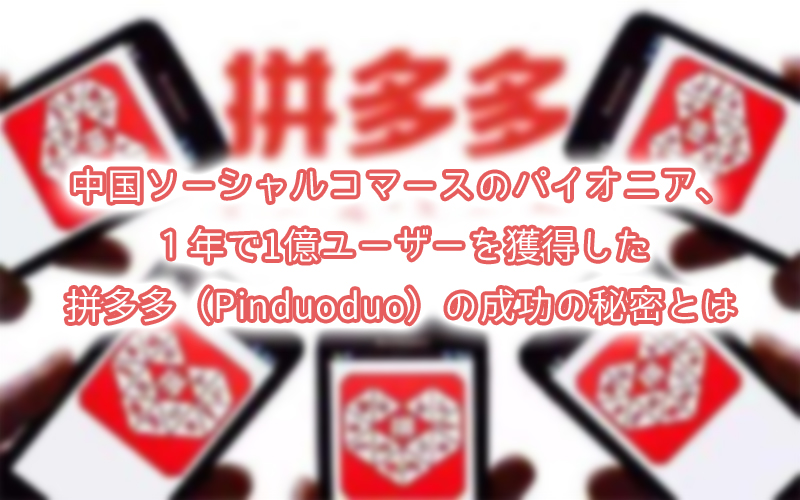日本では2021年に入ってもコロナ渦は収まっておらず、新種とともに再燃しております。
コロナ渦は実店舗に多大な影響を与え、多くの事業者はECで新たな販売チャネルを開いて売上を増加できないかと四苦八苦しているようです。
その一方、いち早くコロナを収束に向かった中国では、大量の出店者がタオバオ(淘宝網)から離脱したとのことです。
その要因と原因を分析しつつ、日本事業者を含めて今後中国ECをどう捉えていくかをお伝えできればと思います。
内部要因
“ビジネスの難しさを取り除き、ビジネスをどこにいてもできる容易なものに“を提唱してつづけてきたアリババですが、インターネットの高度な発展に伴い、タオバオアプリは誰もが使用する基本的なAPPとなっていました。
タオバオでショップを開設して恩恵を受けていた人々はタオバオに依存し続けていました。
2019年の初めにタオバオのショップ数は1100万店に達しましたが、すべてのショップが儲かっているわけではなく、供給過多の側面から極一部のショップしか稼げないとも言える状況となりました。
そんな背景で、もうタオバオで売り上げを立てれない人々が続出し、やがて退場させられました。
以下弊社がまとめた2019年から2021年8月までのタオバオ出店数のデータです。
一番良かった時1,119万店舗、2021年8月時点ですでに1/5以上離脱してしまったとわかりました。

1.Tmall(天猫)の成長に資源を集中したアリババ
小規模企業および個人事業者がほとんどのタオバオに比べて、Tmall(天猫)に出品する際にブランド・商品の品質さらにタオバオに欠けていた「偽物に対する取り組み」を強化していました。
このような厳格な対処に伴い、Tmall(天猫)に登録した信用力の持つ会社、安心してサービスを利用できる消費者を手に入れたと言えます。
中小企業にささげられていたアリババですが、大企業の取り込んで一気に成長し、中小企業と大企業を同じ舞台で戦わせている挙動にさんざん周りから揶揄されました。
11.11、独身の日イベントは中小企業への配慮のなさ
小規模企業と大企業の根本的な違いは商品力などではなく、資金力の格差にあります。どれだけリスクや赤字に耐えられるかの底力の差です。
今まで11.11、独身の日イベントに対してTmall(天猫)に出店した大手企業の売上の報道を見られますが、逆にタオバオではあんまり注目を浴びられていませんでした。

参加しても売れませんでしたということに一言で尽きます。
11.11、独身の日のイベントの本質はアメリカの「ブラックフライデー」と似たようなものです。
ビッグセールを実施して各店舗の集客をサポートしている存在のはずですが、参加する場合は、必ず最低でも「10%offしてね」というルールも存在していました。
また、店舗を跨ぐ購買は合計金額が400元を超えたら50元割引などの割引制度も導入された時期もあり、割引額の半分は出店者側が負担し、実質25元の割引を強いられていたというところです。
中・大規模の企業では容易く参加はできるものの、中小企業は取り越し苦労になる可能性あるなかで無理やり参加してしまった出店は大勢いました。
出店者の中には2か月の利益が無い状態で運用していた店舗も存在していました。
さらに11.11、独身の日のイベント、それの次に来る12.12のイベントも同様、6月以降になると、あれがほしいけど今すぐ買わなくてもいいやという商品を我慢して年末商戦の時に一気に買う傾向が中国のECにおいて顕在化になりつつあります。
参加せざるを得ない、参加しても儲からないという矛盾に置かれているのが中小企業の苦境です。
2.本格的なEC運用に伴うコストが高騰
売れている店はどんどん売れるAmazonのベストセラーのような仕組みとほぼ同じ、検索した結果は広告以外は、ほとんど売れている商品ばかりです。
タオバオは自分自身の利益を考えて売れている商品をおすすめしているので無理はありません。
タオバオ全体の出品数と少しずつ離れていくユーザーとの割合、その供給関係が崩壊している今、後から入ってきた事業者にはタオバオ内の広告を使わない限り、苦しむしかほかありません。
ネットショップとリアルショップは店の賃料、光熱水費や店で働くスタッフの人件費などを計算したら、どうしても前者のほうがコストが安いと思いがちですが、競争がどんどん激しくなってきた中国ECにおいては、流入問題をどう解決するか悩む課題です。
・ネットショップ内のSEO、ショップ外のソーシャルツールの駆使
・いかにクリックしてもらえるかプロによる商品デザイン、商品写真の撮り直し
・刺さるコンテンツを満載したランディングページ
・3分間以内返信しなければならない常時チャット対応
・レビューやアフターサービスに対して素早く対応
これはスタンダードと言えるほど莫大な固定費用を負担して成し遂げてはじめてチャンスがあるということであれば、もうリアルショップで地利を活かし、オフラインとソーシャルECのコンビで逆にし易いかもしれないという思い始めた人たちが続出しています。
外部要因
3.電子商取引税の立案
現在、中国ではモバイルインターネットの急速な発展に伴い、インターネットやスマートフォンの普及で国民のライフスタイルも変化しています。
また、大多数の人々の買い物の習慣は、物理的な買い物からオンラインショッピングへと移行しており、多くのEコマースショップの売上は徐々に増加しています。

昨年12月には、国家税務総局から課税対象ECプラットフォームに一定期間内に電子商取引の国家税務データ分析システムの開発・展開を完了させることを求めていると発表がありました。
これは、電子商取引の課税が標準化される最初の一手となります。
ネットショップにてトラフィックの増加や、おすすめに掲載されることが目的で、お金をかけて偽取引数を不正闇業者から獲得したとしても、その分も課税対象となることを意味しています。
元々薄利であるタオバオ事業者たちから、さらにお金が取られるしまうということになり、EC税金対策なども間もなく波紋になるでしょう。
4.拼多多(ピンドゥオドゥオ)などのECライバルの台頭
商品を安く買えるという売りはほぼタオバオのブランド認知とユーザー人物像が合致しているといわれています。
拼多多の爆発的な成長により、すでにタオバオを凌駕する勢いです。
それと同時に、WeChat、Tiktok、レッドブックなど様々なソーシャルメディアでもEC化に進化し、微力ながらC2C市場のシェアを少しずつ奪おうとしています。
個人事業者はほぼコストがゼロで出店できるようになった今、タオバオが誇るC2Cの王者そのものが議論される余地がありました。
言い換えれば、現在中小企業や個人事業者でもECを行うなら、昔みたいにタオバオ一択ではなく、さまざまの選択肢から自社にピッタリの道を選ぶことができるということになりました。
拼多多(ピンドゥオドゥオ)について以下の記事で詳しく解説しています。
合わせて読んでいただければ幸いです。
まとめ
タオバオからマーチャントが大量離脱してしまった主な理由を4つ挙げました。
すでに売れているトップ企業と中小企業とのバランスは中国だけではなくEC市場において世界的な課題となっていると思います。
タオバオから離れていった事業者たちは一部倒産したかもしれませんが、ECのやり方に豊富な選択肢が存在する中国ECなら、恐れる必要がありません。
このような環境の中で事業者たちは、自分たちの負担できるコストの範囲でA/Bテストを実施して、売上を確実に創出できる最も有利なECプラットフォームを探し出す必要があるでしょう。
自社ECサイト、モールサイト、またはソーシャルECなど派正したルートも挑戦する価値が残っています。
【PR】
中国ECのやり方がわからない、ノウハウがわからない、コストを算出できないなどご相談ください。
中国越境ECをこれから挑戦したい方はこちらからお問い合わせください。